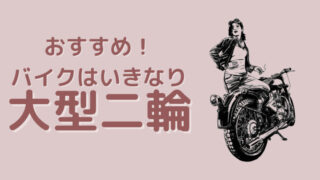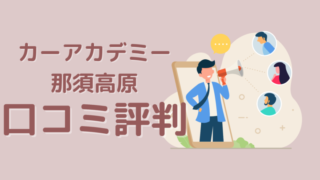- 車の免許を取ろうと考えている
- 男は黙ってマニュアル免許を取るべき?
- マニュアル免許が必要な理由があれば知りたい
そんな悩みにお答えします。

この記事を書いている僕は、教習所の教官として12年勤めていました。
結論から言うと、とりあえずマニュアル免許なら絶対いらないです。
男ならマニュアルだ!!
いつか役立つ時がくる!!
僕の世代ではこのような考え方が一般的であり、同級生の中でも男でオートマは1〜2人いるかどうかでした。
最近のお客さんの傾向だと、男性でもオートマ免許を取る人がだいぶ増えてきた印象です。僕が勤めていた教習所でも7割がオートマ希望のため、マニュアル車両の台数を減らしてオートマを増やしています。
この記事では、マニュアル免許がいらない理由を教官の目線で詳しく解説していきます。
【教官が断言】マニュアル免許はいらない【存在意義がないです】

マニュアル免許がいらない理由は、準中型免許においしいところを全部持っていかれたからです。
それでもマニュアル免許が必要な理由を挙げるとすれば、「マニュアル車に乗りたい!」というニーズに応えるためでしょう。準中型免許でもマニュアル車に乗れますが、取得費用が高くなりますからね。
ざっくり料金を比較すると、以下のとおりです。
- マニュアル免許→税込30万円前後
- 準中型免許→税込35万円前後
教習所によって金額に違いはありますが、マニュアル免許と準中型免許の金額差は5万円前後です。
免許を取る人の傾向としては、5万円の価格差なら上位免許を取ったほうが何かと役立つと考える方が増えているように感じます。
準中型免許とは?
2017年3月12日に、新たな免許区分として追加されたのが準中型免許です。
- マニュアル免許と同じく18歳から取得できる
- 俗に言う「4tトラック」が運転できる
この2つが、準中型免許の大きな特徴と言えます。
近年、トラックドライバー不足と言われているのが日本の物流業界の現状です。18歳でも4tトラックが運転できるようになる準中型免許は、当初に想定していたよりも “需要大” でした。
そんな準中型免許とマニュアル免許の違いを、教官の立場で比較していきます。
マニュアル車がいらない理由①:実用性がほとんどない
プライベートで乗る車のほとんどは、オートマチック車になるでしょう。マニュアル車に乗る機会と言えば、軽トラックを運転するときくらいです。
マニュアル車を仕事で使う機会も少ない
マニュアル免許をあえて取りにくる理由のひとつに、
就職先で役立つと思ってマニュアルにしました!
こんなのがありますね。しかしマニュアル車を職場で使う機会は、年々減少傾向にあります。
僕は年間2,000人ほどのお客さんを教習していましたが、結局のところ仕事先でもオートマ免許で十分だったという報告が大多数です。
普通車のマニュアル免許だとトラックドライバーにもなりにくい
現行の普通マニュアル免許で運転できるトラックは、2tトラックまでです。2tトラックを主力としている運送会社は、それほど多くありません。
深刻なトラックドライバー不足を解消するために、2021年から厚生労働省と全日本トラック協会がタッグを組んで、ドライバー育成支援プロジェクトを実施しています。
その対象免許も、以下のとおりです。
- 準中型免許
- 中型免許
- 大型免許
ここに普通マニュアル免許は含まれていません。運送会社としては、トラックドライバーとして戦力になるのは準中型免許からと考えているわけです。
- 運送会社で内定を受けてから準中型免許を取るのがおすすめ
- ドライバー育成支援プロジェクトにより、運送会社に補助金が出ます。社員の免許費用の一部を負担してくれるので、マニュアル免許よりも安く準中型免許が取れる可能性がありますよ。
すべての運送会社が対象ではないので、参考程度に知っておきましょう。
タクシー会社も最近はオートマ車が増えている
タクシードライバーを目指す人にとっては、マニュアル免許を取る選択は悪くないでしょう。しかし、タクシー業界もオートマチック車を使用する会社が増えています。
マニュアル車を運転できた方が、就職の幅が広がる可能性もあるかも知れません。しかし僕が勤めていた教習所では、普通二種を取る人の8割以上がオートマ免許でした。

今後は自動運転も普及していくので、マニュアル免許の価値はどんどん低くなっていくと考えられます。
マニュアル車がいらない理由②:使う予定がないと操作を忘れる
とりあえずでマニュアル免許を取った先輩たちに聞いてみてください。
十中八九、NOと答える人ばかりだと思いますよ。使わなければ忘れてしまうのは、仕方がないことです。
「とりあえずマニュアル」の多くは操作を忘れてしまう人ばかりなので、忘れてしまう知識にお金をかけるのはもったいないでしょう。

必要になったタイミングでAT限定解除するのがスマートです。
マニュアル車がいらない理由③:免許費用が追加になるリスクがある
マニュアル免許で運転練習をする時間は、初めて免許を取る人で最低34時間です。そのうち、教習所のコースを使って仮免許を取るための練習時間は最低15時間になります。
つまり15回の練習で、以下の能力を身につける必要があるわけです。
- マニュアル車の操作を覚える
- マニュアル車をコントロールできる
- 運転席から見えない部分がイメージできる
これらが身に付いていないと、検定に合格できません。不合格になれば、追加料金が発生します。
検定不合格時の追加料金
- 補習教習1回以上(1回あたり4,000〜8,000円)
- 再検定の受検料金(5,000〜8,000円)
教習所によって金額は違いますが、最低でも10,000円以上の出費は覚悟しておきましょう。

とくにマニュアル車は、基本操作が覚えられずに延長となる方が多いので気を付けてください!
準中型免許で試験に落ちる人はごくわずかです
準中型免許は、マニュアル免許に比べて教習時間が長いのが特徴です。
準中型免許で運転練習をする時間は、初めて免許を取る人で最低41時間。そのうち、教習所のコースを使って仮免許をとるための練習時間は最低18時間となります。
マニュアル免許と比べて3時間分多く練習できるので、運転技術がしっかり身に付きやすいということです。
準中型免許もマニュアル免許も同じ試験内容
準中型免許はトラックを使用し、マニュアル免許は乗用車を使用するのに、試験で使うS字やクランクの課題は同じ場所を使います。
一見するとサイズが大きい準中型免許の方が難しそうに感じますが、準中型トラックはミラーですべての状況を把握できるため、試験合格率が極めて高いです。
準中型トラックとマニュアル車で、それぞれの運転席からの見え方を確認してみましょう。


準中型トラックのほうがコース全体を把握しやすいのが分かるでしょう。マニュアル車に比べてミラーも大きいため、縁石と車体の幅間隔も確認できて課題の通過が楽です。
一方でマニュアル車は準中型トラックと比べて前方部分の死角が大きいため、乗り上げや接触を起こして試験失格になる人も少なからずいます。
追加費用がかかりにくいのは、圧倒的に準中型免許です。
まとめ:マニュアル免許はいらない ⇒ オートマで十分

マニュアル免許は、準中型免許の登場で実用性がほとんどない免許となりました。「とりあえずマニュアル取ろうかな」程度の気持ちであれば、オートマ免許の取得を強くおすすめします。
僕の時代のマニュアル免許は、今よりも乗れる車の種類が豊富でした。その名残りで、「男ならマニュアル」と考える親御さんもまだまだいます。
| 平成19年までのマニュアル免許 | 現在のマニュアル免許 |
|---|---|
| 車両総重量8トン未満までOK | 車両総重量3.5トン未満までOK |
| 最大積載量5トン未満までOK | 最大積載量2トン未満までOK |
| 乗車定員は10人までOK | 乗車定員は10人までOK |
昔のマニュアル免許は、今の準中型免許と同等の立ち位置でした。
しかし現在のマニュアル免許で運転できるのはほぼ乗用車のみにもかかわらず、よく調べもせずに「とりあえずマニュアル」っていう親御さんがまだまだ多いですがムダ金です。
とりあえずマニュアルがムダ金になる理由
- 教習の追加料金が発生するリスクがある
- 免許取得後に使わないから忘れるリスクがある
- 「いずれ役立つ」のいずれはほとんど来ない
車を運転するだけなら、オートマ免許で十分です。マニュアル免許にしておきたいなら、幅広い車に乗れる準中型免許を検討しましょう。
近くの教習所より合宿免許の方が安く取れる
意外に思うかも知れませんが、宿泊代や食事代込みでも合宿免許の方がかなり安いのでおすすめです。同じ教習所でも合宿の方が料金を下げていますからね。
太郎益田さん/
みなさん仰られるように合宿だったらここでいいかもしれませんが、通いだったらここじゃない方がいいと思います。スケジュールも合宿生が優先ですしね。あとは単純に代金が高いです。宿泊費と弁当代がついているはずの合宿生よりも高いですからね。
Google口コミ
評価の高いレビューは合宿の思い出補正でしょう。
こちらは合宿教習所として人気No1の六日町自動車学校の口コミになります。
こちらの教習所で普通免許ATを取る場合の金額は、以下のとおりです。
同じ教習所で同じ免許を取るのに、130,000円以上の価格差があるわけです。
そりゃあ通学生から不満が出るのも納得できますが、全国どこの教習所でも同じ対応が取られています。
通学で免許を取るのははっきり言って損なので、まとまった休みが取れるなら合宿免許を検討してみることがおすすめです。
合宿免許の注意点
- 合宿免許は定員制
- 長期休暇は予約枠がすぐ埋まる
- 人気の教習所は予約枠がすぐ埋まる
合宿免許はとにかく安いので、人気の教習所には予約が殺到します。
合宿免許の予約は1〜2ヶ月前に済ませておくのが一般的なので、早すぎることはありません。定員に達する前に、教習所の予約枠を確保しておきましょう。
当サイトでは、教官歴12年の筆者がリサーチした人気の合宿教習所を、車種ごとに紹介しています。下記リンクから希望する車種の教習所ランキングをチェックしてみてください。
【普通免許】

17歳から合宿に参加可能です。教習所で嫌な思いをしたくない方は必見!
【小型二輪免許】

16歳から取得可能な小型二輪免許!125ccまで乗れますよ!
【普通二輪免許】

16歳から取得可能な普通二輪免許!400ccまで乗れますよ!
【大型二輪免許】

18歳から取得可能な大型二輪免許!すべてのバイクに乗れる最上級免許です!
【普通二種免許】

合宿なら最短7日間で取れますよ!
他車種は後日更新します。
















 【新潟県】六日町自動車学校
【新潟県】六日町自動車学校  【長野県】天竜自動車学校
【長野県】天竜自動車学校  【岩手県】久慈自動車学校
【岩手県】久慈自動車学校